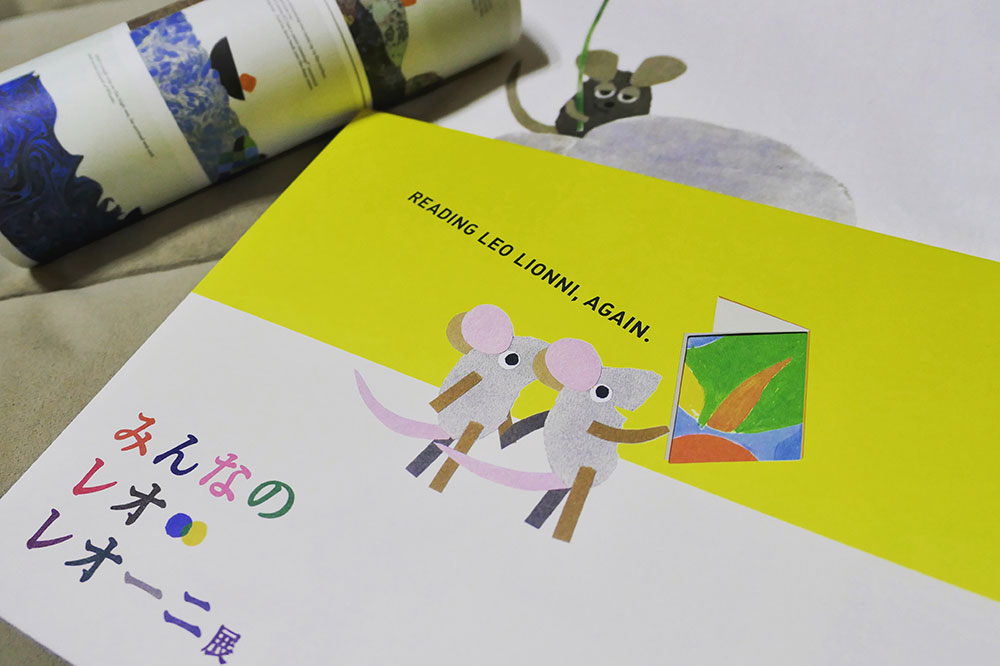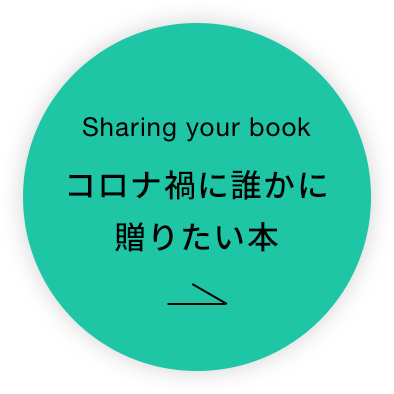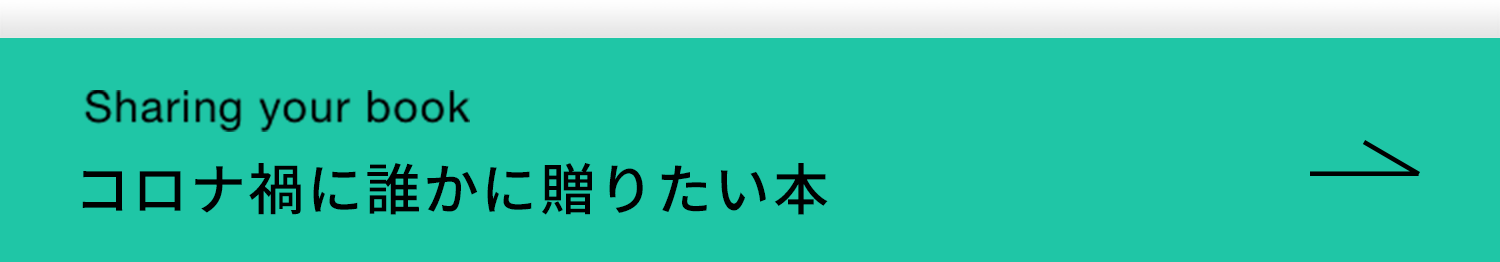| タイトル | おんがくねずみジェラルディン―はじめておんがくをきいたねずみのはなし |
|---|---|
| 著者 | レオ・レオニ(翻訳 谷川俊太郎) |
| 音楽を聴いたことがなかったねずみのジェラルディンは、ある日、台所のすみっこでとても大きなパルメザン・チーズをみつけます。仲間とチーズをかじっていくと、中からチーズのねずみの像があらわれて・・・!? 音楽との出会いと喜び、‘音楽のある世界’で生きることの素晴らしさを問いかける絵本作品。 | |
レオ・レオニとの本当の出会いは大人になってからです。それまでずっと学校の教科書にも取り上げられる絵本作家の人だな〜程度のイメージでしたが、いざ息子が小さい頃に読み聞かせてみたところ、なんだこれ!?すっごい面白い…!と心を掴まれたアーティストです。
大人になって読んでみると、レオニの絵本には強いメッセージ性を感じますが、不思議とそのメッセージをどう受け取るかは読者に委ねられているような寛容な雰囲気もあります。作品ごとに「これは想像しなかった〜〜〜」という驚きがあるんですが、育児をしていく中で、こうしなきゃああしなきゃ…こうあるべき?とガチガチの頭でいたところを一筋の風が通り抜けていくように心を楽にしてくれる作品。子育てはこうあれ、みたいなことは忘れていい。出会えてよかったと思っています。
レオ・レオニの絵本の中で私が一番好きなのはこの「おんがくねずみ ジェラルディン」。音楽と出会った興奮や喜び、音楽を好きになる過程、音楽を知った新しい自分が生まれる瞬間の描かれかたにグッときます。
今、どこに行っても何かしらBGMが流れていたり、ああ音楽流れてるねテレビついてるね・・とついつい溢れている音楽に鈍感になってしまう気がしますが、ジェラルディン(レオニ)の世界ではそうではなく、静寂があるからこその音楽との出会いがあるように思えて羨ましくも思いました。
コロナ禍の今、静寂をまとって言葉の音楽に浸りたい、心を解き放ちたいと思っている人に、谷川俊太郎の翻訳も素晴らしいので、ぜひ音読してみることをお勧めします。
2019年にレオ・レオニ展が開催されたので息子と一緒に観てきたのですが、衝撃的でした。
「石を見ながら描くのではなく、見た石を一旦頭に入れてから、そのあと頭の中の石を描く」という印象的なエピソードもさることながら、1970年代、レオニが架空の植物を描き学術書の形式で発行した『平行植物』という本が衝撃的でした。その架空の植物は「時空のあわいに棲み、われらの知覚を退ける植物群」と定義されていて、SF、ディストピア感、ぶっ飛んでました。メッセージを込めた絵本作品を描きながらも、一方でこんな世界観を持っている不思議なレオニ。興味が尽きません。