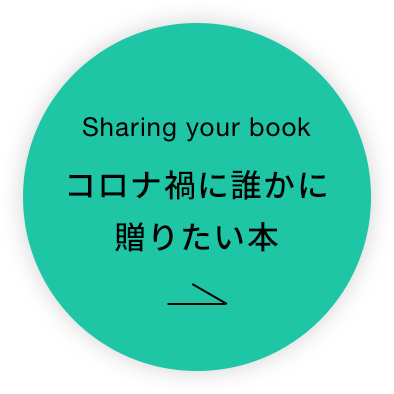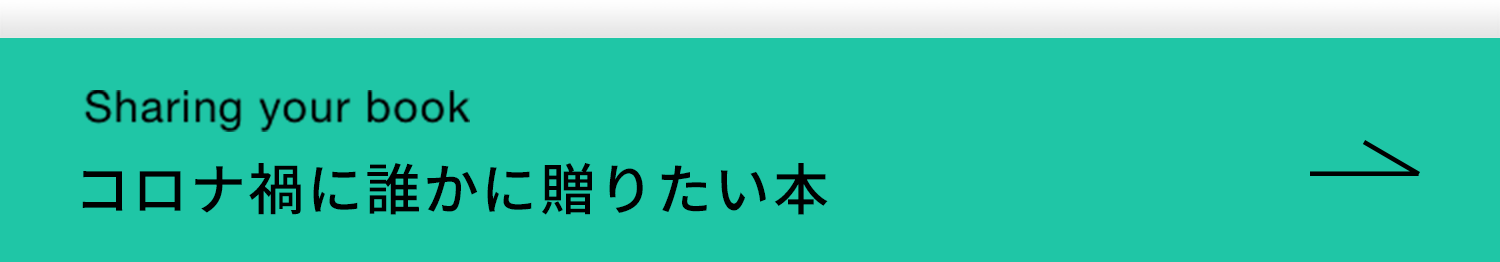| タイトル | 自覚なき差別の心を超えるために |
|---|---|
| 著者 | 宮城顗(しずか) |
| あとがきによれば、この本は1985年前後に真宗大谷派京都教区同和推進本部での講話を編集したものだそうです。人間の持つ罪業性とその中で「生きる」とはどういうことか、その中で差別ということが避けて通れないことであることなどが語られます。ではそれはどのように打破できるのか、というと、宮城氏は「願い」というものに答えを求めます。徹底的に願い続けることが力となるというのです。そのような姿勢で差別と向き合うこと、自分と向き合うことの重要性が語られます。 | |
私がコロナ禍の中で一番気になったことは、自粛警察と呼ばれる行動でした。営業している店に張り紙をしたり、公園で遊んでいる子供にさえ集団でいるなと怒り、東京に子供がいる家庭に子供は帰省するのかとしつこく聞いたり、さまざまなニュースがありました。感染者を出した大学も名前が出され、関係のない学生もアルバイトをクビになったりしては、明日は我が身という思いが強まったものです。民俗学や日本文化という勉強していると、こうした行動は閉鎖的なムラ的な文化の問題かと考えてみましたが、それで解決するようなことでもない、と感じていました。そんな折に出会った本がこの本です。
講話ですので、平易に語られており、いたわりの気持ちがむしろ差別となることが著者の経験からはじまります。目の見えない人と一緒にいてきれいな風景を見たとき、思わず感嘆の声が出そうになったのを目が見えない人を気遣ってその言葉をのみこんだ自分と、それを一生懸命説明しようとする他の同行者たち、ということからいたわりという人間的な行動でさえ差別になることに気がつき愕然とするエピソードです。そこから仏教の地獄は私たちの足元にあることの意味を問い直します。要するに私たちは地獄の上に生きているのだということ、無意識の奥底にすでに地獄を抱えているのだという罪業性です。先のいたわりの心というのは、ある意味正義でもあるわけですが、それが問題を引き起こしてしまう。自粛警察がそうです。自粛はある意味では正しいのですが、それを振りかざして自分の正しさを他人に押し付けるとき、それは正義ではなくなります。こうした心を「まいらせ心」というのだそうですが、これが一番厄介だといいます。そこをどう突破するのか。それには本当に向かい合うということだといいます。周りの人と向かい合い、ついにはその人から見られている自分というものを受け止めて生きてゆく、ということが大事だとします。それが自分事として感じ取るためには必要なことです。そして、差別ということに関して「人権」ということを考えると、人権とは「人間がめちゃくちゃにされないためのもの」というイーデス・ハンソンさんの言葉が紹介されます。その人がめちゃくちゃにされるということが人権侵害であり、差別だということですが、とても分かりやすい。だから人を平等に取り扱うということは、役に立つとか価値がないとかではなくその人をめちゃくちゃにしないことだと言います。
その他にも良い言葉はたくさんありますが、最後に宮城氏は「本願成就」という言葉に行きつきます。本願成就というと、願いが叶った、というゴールのような意味に捉えられがちですが、願いが叶えば願いは消えてしまう。しかし、そうした願いは本当の願いではない。仏教でいう本願成就とは、願いが力になる事だといいます。願いが力を生み出し、力が願いを新しくしてゆく、そういう無限の歩みを本願成就というのだそうです。その人が生きてゆく事で、その願いが新しく、常に新しくされていく、無限運動だそうです。差別ということが、人間の持つ罪業であるならば、それをなくし平等な世界にすることを願い続け、歩み続ける。これは決して難しいことではなく、たとえば差別から目をそらすことがあっても、それを恥じた自分として生きてゆく、という自覚を持つことだそうです。その自覚なくしては何も始まらないからです。
長くなりましたが、この本は部落差別の問題を取り扱ったものです。コロナ禍でどう生きるか、というために話されたわけではありませんが、「差別」という問題が人間の本質的内在的な課題だと自覚して、自分は違う、人を差別しない、というごまかしの態度ではなく、人と向き合って生きることを教えてくれた本です。普段仏教に触れていないので、経典の言葉の理解に不安はありますが、仏教の生きる指針も悪くはないな、と思わせてくれました。